https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1056734&tstart=644
注)UK_のカーネルはおそらくダウンロードまたは解凍失敗している
→新しいカーネルパッチのファイル名をSAPEXE.SAR SAPEXEDB.SARとして
入れ替えが必要
\FTP conection\
1.#cat /etc/redhat-release
CentOS release 5.6 (Final)
#cp -r /etc/redhat-release /etc/redhat-release.org
#vi /etc/redhat-release
#cat /etc/redhat-release
redhat-4
cat /etc/redhat-release
redhat-4
1.ftp 192.168.1.10
2.azuma/binloony
3.get j2sdkfb-1_4_2_31-linux-i586.bin /media/sap_common/j2sdkfb-1_4_2_31-linux-i586.bin
mount -t cifs //192.168.1.7/disk /mnt/landisk
1.j2sdk install
# chmod 777 *
# cd
#./j2sdkfb-1_4_2_31-linux-i586.bin
IBMJava2-AMD64-142-SDK-1.4.2-13.9.x86_64.rpm
2.path setting
adding following lines in #view .bash_profile
JAVA_HOME=/media/sap_common/j2sdk1.4.2_31
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
EXPORT PATH
3.TEMP setting
#cd /root
#mkdir TEMP
#TEMP=/root/TEMP
#export TEMP
#DISPLAY=WIN2K3R2EE:0.0
#export DISPLAY
4.install by package manager
- compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386
- compat-libstdc++-33-3.2.3-61.x86_64
- libstdc++-4.1.2-50.el5.i386
- libstdc++-4.1.2-50.el5.x86_64
- compat-db-4.2.52.-5.1P_i386
- compat-db-4.2.52.-5.1_x86_64
- sysstat-7...
- libaio-devel xxxx_i836 and x64
- libXp xx all
- gcc ..all
5.create oracle folder
cd /
mkdir -p /oracle/stage/102_64
6.create groups and users
groupadd oper
groupadd dba
groupadd sapinst
groupadd sapsys
useradd -G oper -g sapsys abcadm
useradd -G sapinst -g dba oraabc
view /etc/group
oper:x:501:abcadm,oraabc
dba:x:502:abcadm,oraabc
sapinst:x:503:abcadm,oraabc
sapsys:x:504:
6.extract oracle install package
/media/SAPCAR -xvf /mnt/usb/DB/ORA10/ORx10264.SAR
- OR110264.SAR database
- OR210264.SAR client
- OR310264.SAR clusterware
- OR410264.SAR companion inc jdk
- OR510264.SAR
7.replace new oracle script refering note 819830
extract files to database/SAP and database/Disk1 <- cant found
mv /oracle/stage/102_64/database/SAP /oracle/stage/102_64/database/SAP_ORG
cp -r /media/SAP /oracle/stage/102_64/database/
8.oracle install
system[menu] > Administration > Login Screen > Security > uncheck "Deny TCP Connection to Xserver"
restart
# su
# vi /etc/sysctl.conf
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax=23136829430
kernel.shmall=5242880
kernel.shmmni=4096
kernel.sem=1250 256000 100 1024
kernel.msgmni=1024
vm.max_map_count=1000000
fs.file-max=65536
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65000
net.core.rmem_default=1048576
net.core.rmem_max=1048576
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=262144
refer sap note 1048303
#/sbin/sysctl -p
if its JAVA-STACK
/etc/security/limits.conf
@sapsys hard nofile 32800
@sapsys soft nofile 32800
@dba hard nofile 32800
@dba soft nofile 32800
# chown -R oraabc /oracle
# xhost +
# su -orapyd
DISPLAY=WIN2K3R2EE:0.0;export DISPLAY
TMP=/tmp; export TMP
ORACLE_HOME=/oracle/abc/102_32; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=abc; export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
# cd /oracle/stage/102_32/database/SAP
# ./RUNINSTALLER
/oracle/oraInventory and the installation group as「dba」.
start 19:58 - 20:24
/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh
/oracle/abc/102_64/root.sh
reboot
iSQL*Plus URL:
http://LINUXTEST.localdomain:5560/isqlplus
iSQL*Plus DBA URL:
http://LINUXTEST.localdomain:5560/isqlplus/dba
10.oracle patch inst
# xhost +
# su -oraabc
# DISPLAY=WIN2K3R2EE:0.0
# export DISPLAY
# cd /oracle/stage/102_64/Disk1
/runInstaller -ignoreSysPrereqs
/oracle/abc/102_64/root.sh
start 20:51 -
11.sapinst
# hostname
-> display short hostname
# hostname -s
-> display short hostname
# hostname -f
-> display short hostname
# cat /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 WIN2K3R2EE.localdomain localhost
192.168.1.11 WIN2K3R2EE
- 1 localhost6.localdomain6 localhost6
# su
# SAPINST_JRE_HOME=/opt/IBMJava2-amd64-142
# export SAPINST_JRE_HOME
# DISPLAY=WIN2K3R2EE:0.0
# export DISPLAY
# TEMP=/TEMP
# export TEMP
# ./sapinst
create databaseフェーズでcatproc.sqlフェーズでエラーになる
1.sapinstを停止
2.keydb.xmlで"ERROR"を検索 / OKに変更
3.sapinst continue with old
# SAPSYSTEMNAME=abc; export SAPSYSTEMNAME
# ORACLE_HOME=/oracle/abc/102_64; export ORACLE_HOME
# ORACLE_SID=abc; export ORACLE_SID
# PATH=$ORACLE_HOME/bin:/usr/sap/abc/SYS/exe/run/:$PATH; export PATH
# LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
# su - oraabc
# lsnrctl start
# sqlplus / as sysdba
# startup
# /usr/sap/abc/SYS/exe/run/startsap DVEBMGS00
SAPSYSTEMNAME=abc; export SAPSYSTEMNAME
ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=/oracle/abc/102_64; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=abc; export ORACLE_SID
PATH=$ORACLE_HOME/bin:/usr/sap/abc/SYS/exe/run/:$PATH; export PATH
TNS_ADMIN=/usr/sap/abc/SYS/profile/oracle
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
[hostname change]export SAPSYSTEMNAME
view /etc/sysconfig/network
view /etc/hosts
[check RAM size]
free
[OS version Check]
cat /etc/*-release
[kernel version check]
uname -r
[kernel parameter check]
/sbin/sysctl -a
[Activated HW dirviers]
lsmod
[check Shared memory file]import -frame capture006.jpg
df -k /dev/shm
[if NFS is running]
service nfs status
service portmap status
[routing info]
netstat -r
fdisk -l /dev/sdb
sdb: sdb1
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/usb -o force
[screen shot]
import -frame capture006.jpg
r
printenv
[rpm]
install
rpm -ihv xxxxxxx
uninstall
rpm -e xxxxx
find
rpm -qa | grep xxx
ps -ef | grep ora
CPU usage
#vmstat 1[interval sec] 10[times]
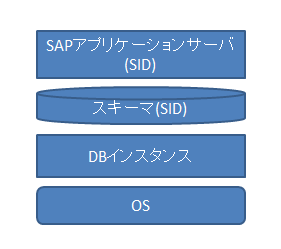
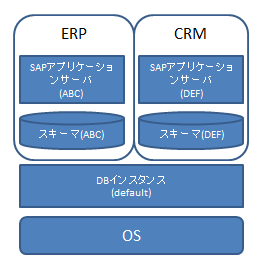
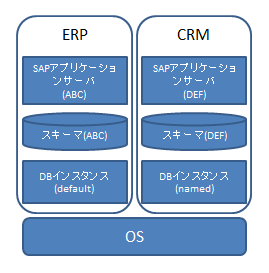












![Google NEXUS 5X 32GB QUARTZ(White) LG-H791 SIMフリー [正規品] Google NEXUS 5X 32GB QUARTZ(White) LG-H791 SIMフリー [正規品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DzQpzj40L._SL160_.jpg)









